こんにちは、ひろりんです。
今日は暖かかったですが、夜はもう寒くなってきましたね。
それと、早いところでは、今日から前回147回の日商簿記1級の合格発表が始まったようです。
前回の試験は本当に難しい内容だったと思います。
受かった方は合格報告をお待ちしていますね。
さて、今日は前回の続き、「長期の安全性」についてです。
安全性について
前回は短期の安全性について3つの指標がありました。
覚えてますか?
流動比率・当座比率・手元流動性比率の3つです。
ここで問題です。
当座資産とはどんな資産でしたでしょうか?
手元流動性に含まれる資産はどんなものがありましたか?
前回の記事を参考にしながら、是非考えてみてくださいね。
長期の安全性分析
- 固定比率
- 固定長期適合率
- 負債比率
- 自己資本比率
固定資産÷純資産(自己資本)
固定資産÷(固定負債+純資産)
負債÷純資産(自己資本)
自己資本÷負債純資産合計
固定比率は、「純資産」に対する「固定資産」の大きさの比率です。
固定資産といえば、何を思い浮かべますか?
建物?機械?備品?たくさんありますよね。それらは大抵、長期間の使用を想定されてますよね。
そこに投資するにはどんなお金を使うべきか。
例えば1,000万の建物を買うとします。
資金をどこから調達するのがいいでしょうか?
短期借入金として借りますか?それではすぐに返済期限が来てしまいますよね。
では長期借入金?ありといえばありですが、所詮、「他人資本」ですよね。
であれば、「自己資本」で払ったほうがいいと思いませんか?
自己資本といえば、返済義務のないものです。(配当金の話とかは抜きにしますね)
固定比率とは、その自己資本でどのくらい固定資産をカバーできてるか。
そこを評価する指標です。
できるだけ固定比率の値は小さい方が良好とされていますね。
仮に自己資本が5,000万あるとします。固定資産は建物1,000万です。
となると、固定比率は 1,000万÷5,000万×100=20% ですね。
次に固定長期適合率です。
これは固定比率の分母である「自己資本」に「固定負債」をプラスしたものです。
上の例でいえば、長期借入金をプラスして、どのくらい固定資産をカバーできてるか。
仮に長期借入金が3,000万あるとします。
となると、固定長期適合率は、1,000万÷(3,000万+5,000万)×100=12.5% ですね。
次は負債比率です。
負債比率は「負債」と「純資産」のバランスの指標です。
言い換えれば、他人資本と自己資本のバランスです。
他人資本は外部から調達してきた資金であり、返済する義務があります。
となれば、負債比率は低いほうがいいと思いませんか?
上記の例を続けて、長期借入金(負債)3,000万、自己資本5,000万とします。
負債比率の計算は 3,000万÷5,000万×100=60% ですね。
最後に自己資本比率です。
ここまで読んでいただければ、これはわかりやすいと思います。
自己資本は返済義務のない資本です。値は高いほうがいいはずですよね。
ここも上記の例の値を使います。負債3,000万、自己資本5,000万です。
5,000万÷(3,000万+5,000万)×100=62.5%
まとめ
長期の安全性分析には主に4つの指標があります。
固定比率・固定長期適合比率・負債比率・自己資本比率です。
短期の安全性分析でも同じですが、何を何でカバーしているのか、が大事です。
計算式の分母に何を使うのか、分子に何を使うのか。
自分がコンサルタントになった気分で、どうなれば良好な値になるか意識しながら勉強するのも面白いかもしれません。
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
ひろりん


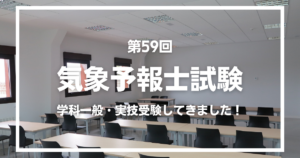







コメント