こんにちは、ひろりんです。
年が明けて、お仕事や学校が始まった方も多いでしょうか?
明日は4月の気温だそうです。体調崩さないように気をつけてくださいね。
さて、今回は備忘録的な内容です。
実は日商簿記1級まで取得しても、財務諸表が「読めない」ということに悩んでました。
ここでいう「読めない」というのは「分析できない」という意味です。
財務諸表の個々の金額は計算できても「そこから何が問題なのか」をきちんと把握したいなと思ったわけです。
以前から財務分析には興味ありましたが、なかなかまとまった時間で勉強できませんでした。
そこで、受ける受けないは別にして「ビジネス会計検定」の勉強をしながら財務分析にトライしてみようと。
タイトルにもありますが、あくまで備忘録的なものなので、かなりざっくりしています。
詳しい説明は他にたくさんサイトがありますから、そこに譲ります(笑)
ただ、アウトラインとしては間違った内容ではないと思います。
全経上級の財務分析対策でもイメージとしては使えると思いますので、参考にしてみてくださいね。
まずはこちらから。
安全性について
安全性の面からの分析です。
さらに細かくは短期の安全性と長期の安全性に分かれます。
(長期の安全性については別記事にします)
短期の安全性分析
- 流動比率
- 当座比率
- 手元流動性比率
流動資産÷流動負債×100
当座資産÷流動負債×100
(現金預金+売買目的有価証券)÷(売上高÷12)
流動比率というのは、流動負債を流動資産できちんとカバーできてるか、という指標です。
流動負債というのは買掛金だったり、支払手形だったり、比較的短期で返済するものですよね。
その返済にあてるお金はどこからもってくるか?
短期で回収できる見込みのある流動資産できちんと返済できるか。
具体的には売掛金を回収して、そのお金で買掛金を支払うイメージです。
一般的には200%以上が安全といわれています。
当座比率というのは、流動資産の中から主に棚卸資産を控除した当座資産を使います。
棚卸資産というのは、材料だったり、仕掛品だったり、すぐに売れないものも含まれています。
売掛金とか受取手形と比べてみて、棚卸資産はすぐに売って、現金化できないですよね。
一般的には100%以上が安全といわれています。
手元流動性比率の手元流動性には現金預金と売買目的有価証券が含まれます。
売買目的有価証券はいつでも売れますし、手元流動性比率は当座比率よりもさらに現金に近い感じがしませんか?
この比率の単位は「月」です。
分母の売上高を12分割していますが、これは仮に売上がなくても、分子の現金預金と有価証券でどのくらい持ちこたえられるか、の判断にも使えます。
まとめ
短期の安全性を分析する指標には主に3種類あります。
流動比率・当座比率・手元流動性比率。
カバーする手段(資産)が何であるのかをそれぞれの指標で気をつける必要があります。
そこさえ間違えなければ、考え方は同じだと思うので、忘れにくいと思います。
次回は長期の安全性について、です。
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
ひろりん



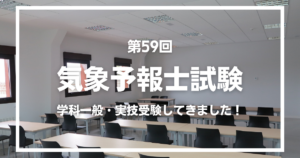







コメント